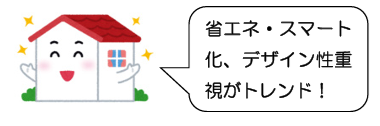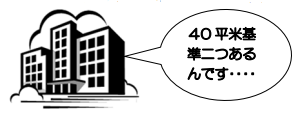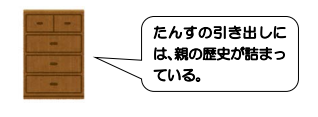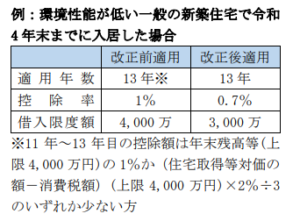原則は契約書の「支払日」で計上 地代・家賃の収入計上時期
原則は契約書の「支払日」で計上 地代・家賃の収入計上時期
その年に「収入すべき金額」を計上する
不動産の個人オーナーの確定申告では、不動産を賃貸したことにより受け取った賃貸料(地代・家賃)を不動産所得の総収入金額に計上します。この場合の計上時期のルールには、次のようなものがあります。
原則は「契約に定められた支払日」
契約書に「支払日」があるか、ないかにより、次の日が収入の計上時期となります。
契約書に「支払日」 が定められている : その契約に 定められた支払日
契約書に「支払日」 が定められていない : 実際に 支払を受けた日
そのため、契約書に記された支払日(支払期日)や支払方法を確認しましょう。
<事例1>
第〇条 甲(賃貸人)に対し、毎月分の賃料10万円を、前月の末日までに、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。
この場合、翌年1月分の家賃であっても、契約上の支払日(支払期日)は前月(当年12月)であるため、翌年1月分の家賃10万円は、当年の12月に計上すべきということになります(当年末に入金がなくても、未収金を計上し、収入を認識します)。
<事例2>
第〇条 本契約における賃料の支払いは、毎年12月末日までに、1年分120万円を一括して前払いする方法とする。
この場合は、契約上の支払日(支払期日)である当年の12月に、1年分の家賃120万円の収入を一括で認識することになります。
一定の記帳を要件に期間対応で計上できる
ただし、継続的な記帳を行い、一定の要件に該当する場合には、貸付期間に対応する賃貸料をその年に収入計上することを認めています(1月分賃貸料は1月に計上)。
⑴ 事業的規模である場合
① すべての賃貸料につき、継続的して前受収益・未収収益の経理を行い、期間対応部分を収入計上していること。
② 1年を超える期間の賃貸料収入は、前受収益・未収収益の明細書を確定申告書に添付していること。
⑵ 事業的規模でない場合
1年以内の賃貸料について、⑴①要件により、収入計上していること。
⑵の場合、1年を超える期間の賃貸料には適用がありませんので、注意しましょう。