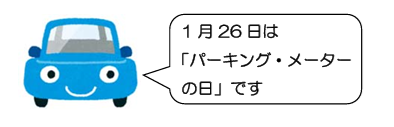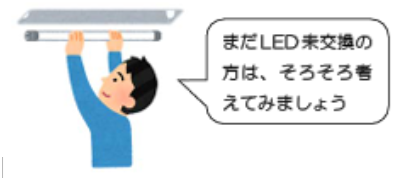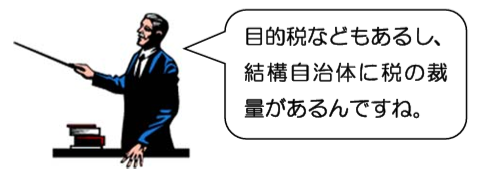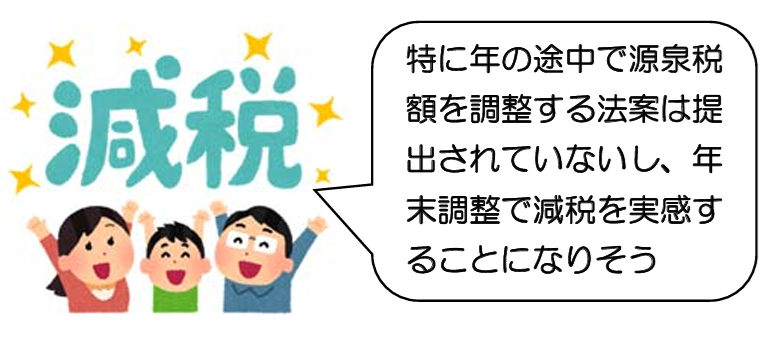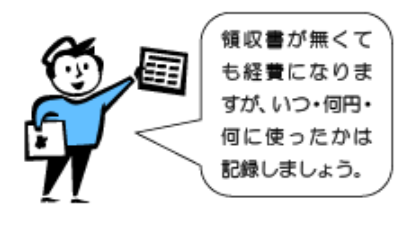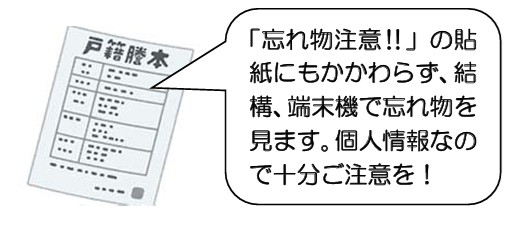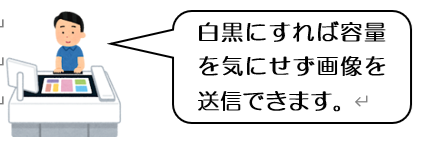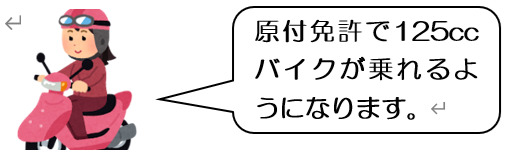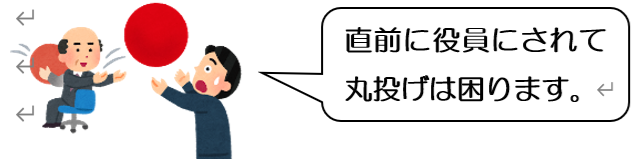駐車料金ではなく、警察手数料? パーキング・チケットの消費税
駐車料金ではなく、警察手数料?
パーキング・チケットの消費税
パーキング・チケットは「警察手数料」
インボイス制度が導入され、しばらく経った頃、「パーキング・チケットは、インボイスが出ない」と話題になりました。繁華街にある道路などの指定された駐車枠内に車両を停め、発給設備に硬貨を入れて、チケットを受け取っているので、てっきり「駐車料金を支払っている」と思っていた人が多いのではないしょうか。警視庁のHPによると「警察手数料(行政手数料)なので消費税は非課税」とのことです。
消費税が非課税となる行政手数料とは?
消費税が非課税とされる行政手数料とは、法令に基づき、国や地方公共団体などが徴収する次のような手数料を言います。
登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付 など
このような手数料は、支払側に選択の余地がなく、税金によってまかなわれるべき行政サービスの費用分担の性格を有するため、消費税を課さないこととされています。
道路法・道交法のルールと消費税
道路に関しては、道路の整備・管理に関する法律である「道路法」と、道路を利用する際の行動・ルールを定めた法律である「道路交通法(道交法)」の規制があります。前者は国交省、後者は警察庁の所轄です。
道交法のいう「道路」とは「一般交通の用に供する道」ですから、交通を妨害するような方法で物をみだりに置く等は許されていません。本来の用途に即さない特別な使用をするときは、「道路使用許可」が必要とされます。道路工事、工作物の設置、屋台の出店、道路を利用したイベント行事などを行いたいときは、道路許可の申請を行います。この時の警察に支払う手数料は非課税となる「行政手数料」です。また、道路を占有するときは、道路法により道路管理者に「道路占有料」を支払います。こちらは、「土地の貸付け」として非課税となります。
「時間制限駐車区間」の駐車を認めるもの
パーキング・チケットの発給設備は、いずれも道交法の「時間制限駐車区間」にあります。この区域では、道路標識や案内板に表示している時間帯に限り、60分以内に駐車をすることができます。指定された駐車枠内に用法を守って駐車していない場合には、駐車違反となります。その場所での手数料ですから、「道路使用許可の支払」という性格が強いということなんでしょうね。