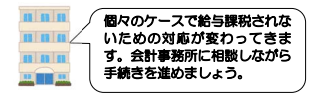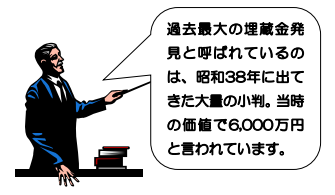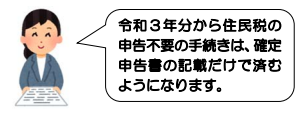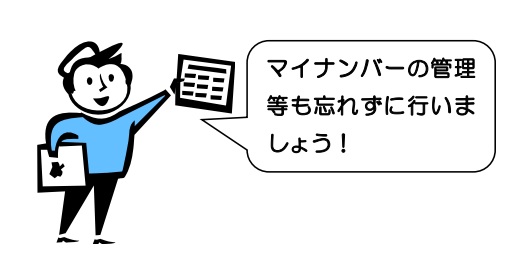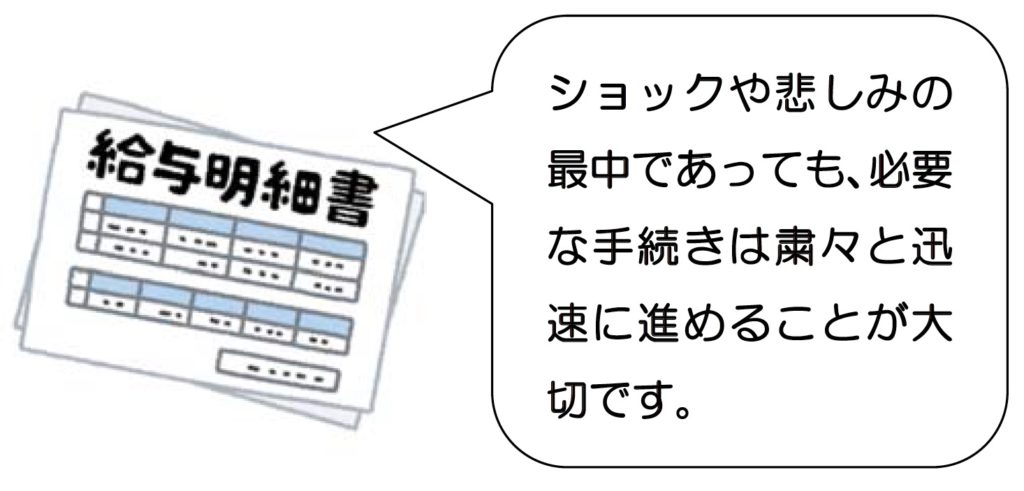ローンを組めない芸能人の
個人事務所が保有する社宅課税
ローンを組めない芸能人の 個人事務所が保有する社宅課税
芸能人は住宅ローン審査で大苦戦
華やかで売れっ子に見えていても、現実には“ローンを組めない”など、意外に厳しい境遇にあるのが芸能人やスポーツ選手です。安定した収入があるサラリーマンとは違い、水物の人気商売の芸能人や稼動期間が短いスポーツ選手に対しては、長期の保証の担保が取れないため、金融機関側も、ローン審査では評価せず、必然的に対応が厳しくなるようです。
売れっ子で現在の年収が億超えであっても、ローンが組めないため自宅を購入できず、“そんな家賃を毎月支払うなら買った方が得”というような高級賃貸住宅に住んでいるのが多いというのはこうした背景事情が影響しているようです。
個人事務所で購入した住宅に住む際の課税
節税のため、個人事務所を作っている芸能人は少なくありません。個人事務所で、蓄積した儲けを使い、事務所名義で取得した住宅に住んだ場合はどのような課税が発生するのでしょうか。節税のための事務所なので、会社形態であり、会社の実質所有者(=役員)がそこに住む芸能人であることを前提とします。
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から 1 か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。
芸能人の豪邸の場合、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅でしょうから、計算される賃貸料相当額は、次のイとロの合計額の 12 分の1 が月額賃料として計算されます。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(法定耐用年数が 30 年を超える建物の場合には 10%)。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
結局、一括購入しても、月々の家賃を支払わないと余計な税金が発生することになるので、賃貸住宅に住む形態となります。
大手事務所の寮や社宅の課税は?
一方、大手事務所が所属する若いタレントを自社が保有する住宅や他社から賃貸した住宅に住まわせているケースでは、賃貸料相当額の計算が変わってきます。
この場合は、使用人として所定の賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。また。食事の提供等がある場合には、それなりの費用の徴収をしなければ給与課税の問題となります。