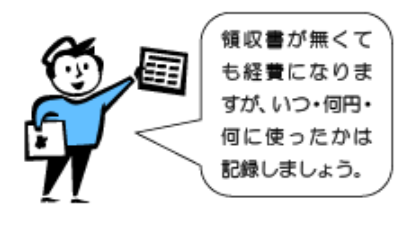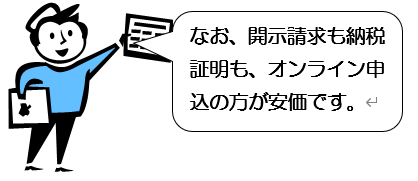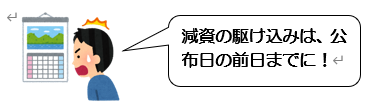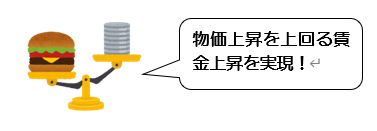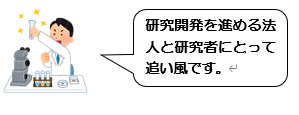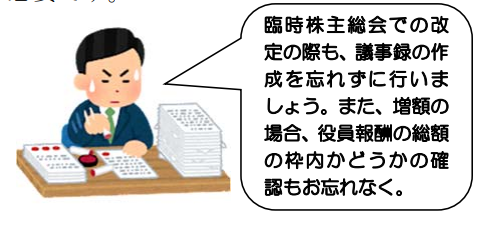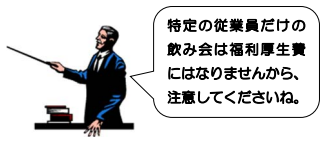-令和8年度税制改正-④ 法人課税編
-令和8年度税制改正- ④ 法人課税編
特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
危機管理投資・成長投資による「強い経済」実現のため、国内で高付加価値化型の設備(特定生産性向上設備等)に大胆な投資を促す税制が創設されます。
国の確認を受けた日から5年経過日までに取得価額の合計額35億円以上(中小企業者等は5億円以上)およびROI(投資利益率) 15%以上の設備投資を行う法人は、投資額100%の即時償却または取得価額の7%(建物、附属設備、構築物は4%)の税額控除(法人税額の20%を上限)を選択できます。一定の要件を満たす場合には、控除限度超過額は3年間の繰越しができます。
試験研究に係る税額控除制度の創設
研究開発税制に新たな制度が設けられます。産業技術力強化法の重点研究開発計画の認定を受けた法人が5年以内に重点産業技術(AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙)に係る試験研究を行った場合には、試験研究費の額の40%(特別重点産業技術試験研究費については50%)の税額控除(法人税額の10%を上限)を受けます。試験研究費の額が前期を上回る場合は、控除限度超過額は3年間、繰越しできます。
オープンイノベーション促進税制は拡充
オープンイノベーション税制は、M&A型の拡充等を行ったうえで2年延長します。M&A型はスタートアップの発行済株式の50%超(上限200億円)を取得した法人が株式取得価額の25%以下の金額を所得控除できる制度です。令和8年度改正では、3年以内に出資割合50%超となる見込みの場合においても、株式取得価額の20%以下の金額を所得控除できるようになります。
賃上げ促進税制は大企業向けを廃止
賃上げ促進税制は、賃上げが順調に進む大企業向けを適用期限を待たずに令和8年3月31日をもって廃止。中堅企業向けは、より高い賃上げを促す下記の要件を強化したうえで令和9年3月31日をもって廃止します。
① 税額控除率10%の適用要件:給与支給額の増加率4%以上(現行3%以上)
② 継続雇用者の税額控除率の加算措置:給与支給額の増加率5%以上で5%加算、増加率6%以上の場合は15%加算
中小企業向けは、防衛的賃上げに取り組む企業に配慮し、現行制度を維持します。
なお、教育訓練費を増加させた場合の上乗せ措置は廃止されます