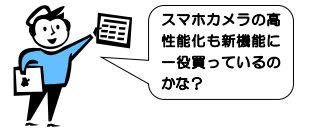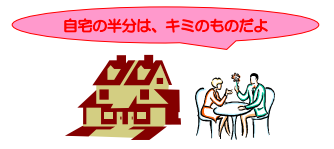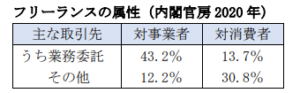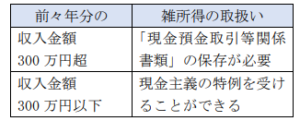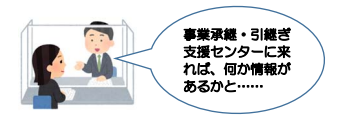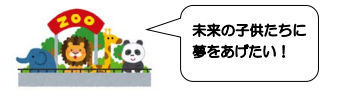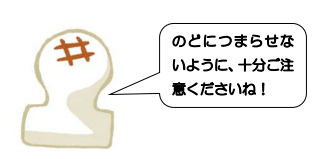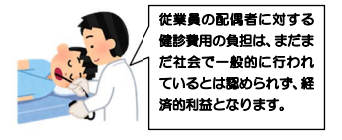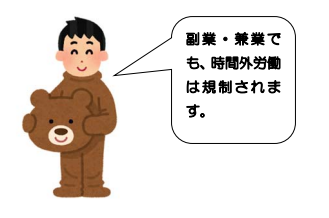令和3年分申告書等作成コーナー新機能
令和3年分申告書等作成コーナー新機能
気が早いかもしれませんが
国税庁のホームページで毎年刷新される確定申告書等作成コーナー。近年は電子化や利便性向上を物凄い勢いで進めています。
少し気が早いかもしれませんが、国税庁はすでに令和3年9 月に、新機能を発表していますので、ご紹介いたします。
スマホ専用画面の対象範囲拡大
新たに特定口座年間取引報告書・上場株式等の譲渡損失額・外国税額控除が、スマホ専用画面の対応となりました。
給与収入と、ある程度の投資をしていらっしゃる方でも、スマホ画面からの申告が行いやすくなりました。
マイナンバー読み取り方法の追加
パソコンで申告書を作成される方も、スマホアプリでパソコン上に表示される 2 次元バーコードを読み取れば、IC カードリーダライタを使用せず、マイナンバーカード方式による e-Tax 送信ができるようになります。
今までのようにカードリーダーを買ったり、スマホを PC に接続して使えるように設定したりという事前のセットアップが不要となります。ただし、お使いのスマホが、ICカード読み取りに対応していなければならないので、ご注意ください。
これが欲しかった! 源泉票撮影で自動入力
スマホ申告ですと、今までは源泉徴収票の内容をポチポチと入力していたのですが、スマホのカメラで源泉徴収票を撮影すると、自動入力される機能が追加されます。便利な機能がついに来ました。この機能の対象が拡大してゆくと、ほとんどの部分で入力を手動で行う必要がなくなるのではないでしょうか。
マイナポータル連携の種類増加
令和 3 年分申告から、ふるさと納税と地震保険がマイナポータル連携の対象となります。マイナポータル連携は、発行元が連携対応している必要がありますが、事前設定しておけば、各種証明書の情報を自動入力してくれるようになります。
なお、医療費通知情報(保険診療分)は令和 4 年分申告以降に、1 年間を通したものが取得可能になる予定とのことです。