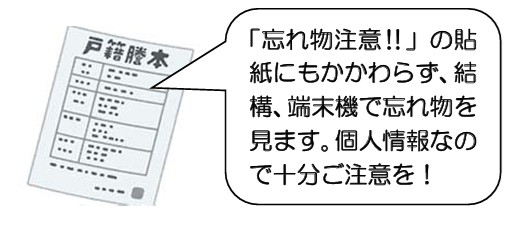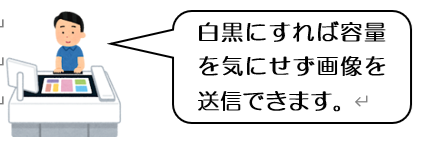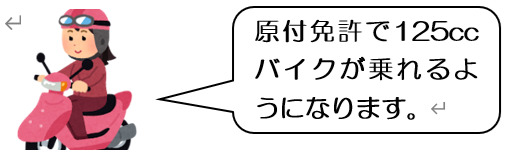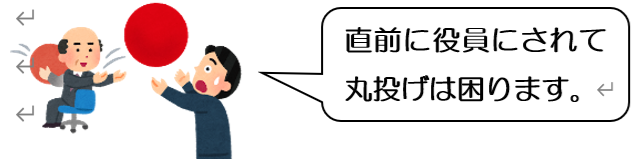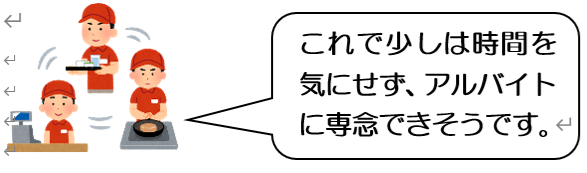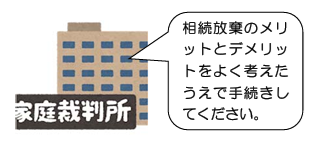戸籍謄本の取得とマイナンバー カード(コンビニ取得は便利です)
戸籍謄本の取得とマイナンバー カード(コンビニ取得は便利です)
2024 年12月従来の健康保険証が不発行に
政府によるマイナンバーカードを利用することを基本とする仕組みにより、従来の健康保険証は、2024 年12 月2日以降新たに発行されなくなりました。また、マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始されます。
マイナンバーカード利用促進の仕組みが次々と実施されていますが、実際にマイナカード利用で便利になったと実感できるものはあったでしょうか?
戸籍謄本等の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まっています。これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになっています。
とはいえ、実際には、市区役所の出張所などでは対応しておらず、本庁舎のある所にまで行く必要があったり、事前予約が必要だったり、さらに手続きをしても書類の入手にも1週間程度かかるなど、まだまだ便利な広域交付とは言い難いのが現状です。
現段階では、本籍地の自治体まで出向くか、郵送取得の方が、簡単で便利です。
コンビニの「証明書交付サービス」が便利
これまでも住民票や印鑑証明書などは、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスがありました。
今般の広域交付により、本籍地を置いてある自治体がこの仕組みに対応している場合、事前登録をすれば、全国のコンビニのキオスク端末で戸籍謄本(抄本)が取れるようになりました。
ただし、はじめて使う時は事前登録が必要で、登録してから本籍地のある自治体での承認事務作業に5営業日は待たなければならないのですが、いったん登録されると、自治体窓口で取得するのと同じ手数料で入手できます。交通費や郵便代などもかからないので、こちらのマイナカード利用はとても便利といえます。
住民税の特別徴収の納付についても当初は対応できない自治体も多かったのですが、今では全国の自治体で対応しています。戸籍謄本の広域交付も全国の自治体に一気に広がるようになるものと期待しています