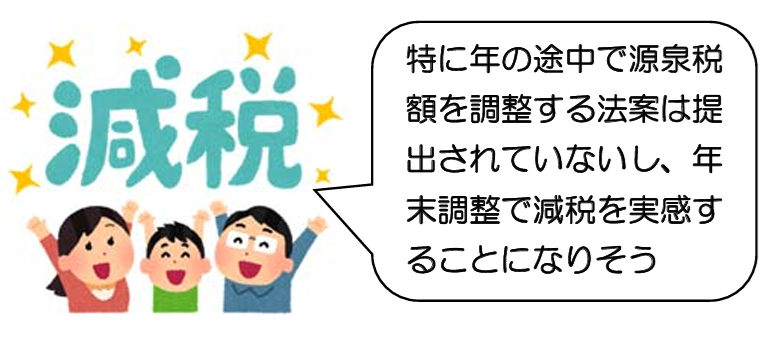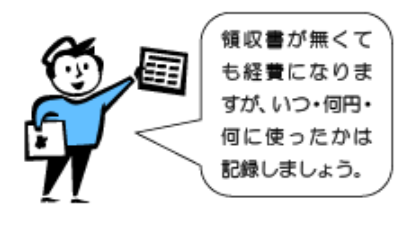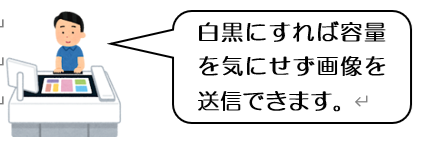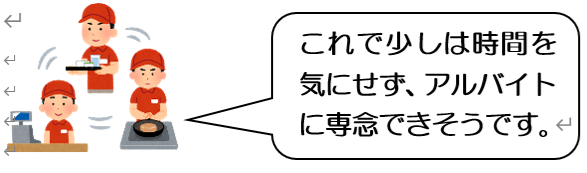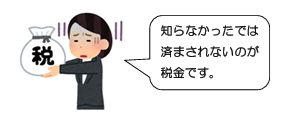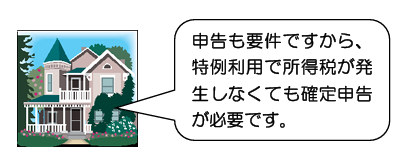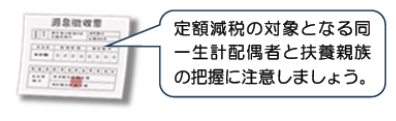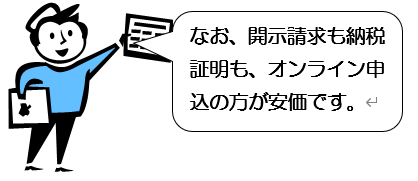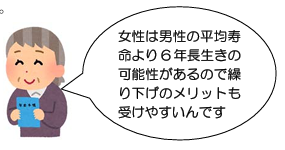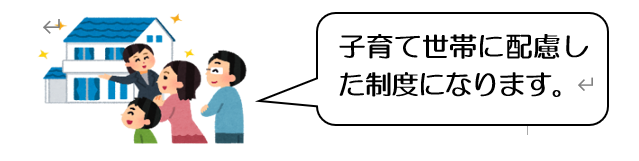実感できない? 年収の壁引上げを感じない理由
実感できない? 年収の壁引上げを感じない理由
103 万円から160万円になるのに
「年収の壁」とは所得税や社会保険加入が必要になる年収のことを指しており、今までだと「103万円の壁」と言えば所得税が課税になるラインのことでしたが、令和7年度税制改正で、基礎控除と給与所得控除の引上げが行われることとなり、今年は「160万円の壁」になるようです。
所得税がかかり始めるラインが上がるだけでなく、今までよりも所得税額が下がるという効果ももちろんあります。ただ、給与収入のある方の中には、今年に入っても「あれ、手取りは別に増えていないな……」と不思議に思っている方がいらっしゃるかもしれません。
発表イコール開始ではない
年末年始に103 万円の壁崩壊のニュースが皆さんの目にとまったのは「税制改正大綱」という「来年こういう風に税制をかえたいんです」という与党の発表があったからです。ただ、発表があったからといって即時にその法案が成立するわけではありません。国会に法案を提出し、それが可決されなければ税の制度は変更できません。
法案が可決されれば「今年 1 月から160万円の壁にする」という遡及が行われるわけですが、源泉徴収する金額も法によって定められていますから、年末年始の発表の時点から「じゃあ年始から源泉徴収する金額を減らそう」と変更するわけにもいきません。今年初頭からの制度変更はできないのは税制改正大綱でも織り込み済みで「源泉徴収税額については令和8年1月から変更します」と記載されています。よって今年の月々に徴収される所得税の額は、去年ベースで計算されたものとなります
年末調整で戻る税金が多くなる
給与収入や社会保険料控除等の基礎控除以外の所得控除の額が変わらないという前提で考えてみると、今年は去年よりも「(定額減税を除けば)源泉徴収で過剰に所得税を取られている状態」になっているため、今年の年末調整で戻ってくる税額が多くなります。去年の定額減税のような、年途中での減額の方が見栄えもするし良かったのでは、という声もちらほら聞こえます。