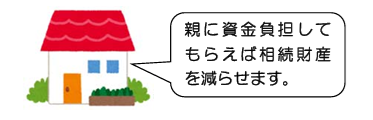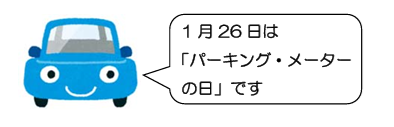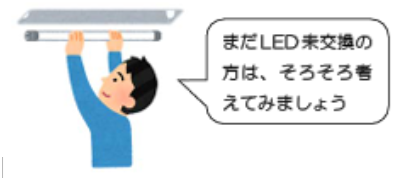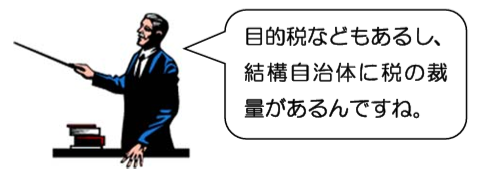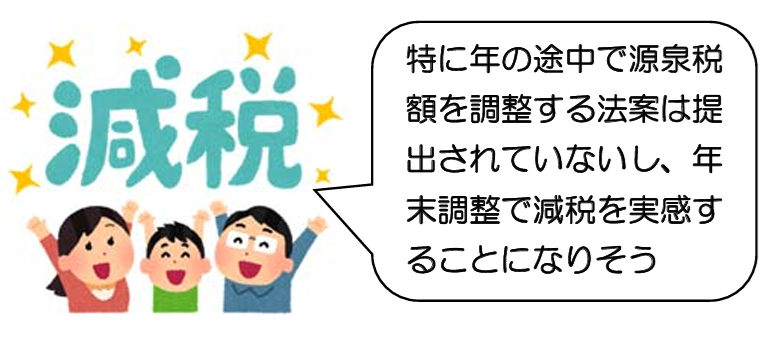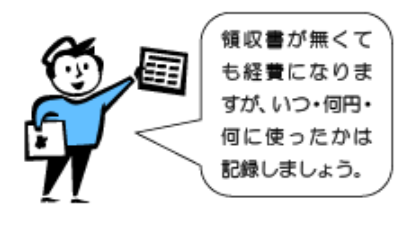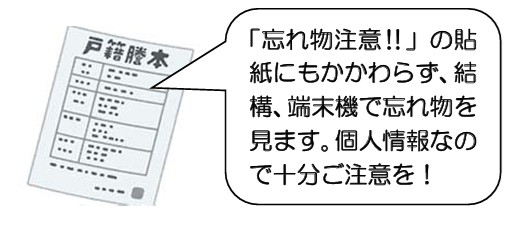親の自宅を子が リフォームした時の課税
親の自宅を子が リフォームした時の課税
親の自宅をリフォームするときに、子が工事代金を負担すると、建物は親の所有物であるため、贈与税が課税されます。
リフォーム部分の所有権は親に帰属する
民法には不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する取扱いがあります。「従として付合した」というのは、不動産に付着しているものをいい、子が工事代金を負担したリフォーム部分は建物本体に付着しており、分けることはできないので、そのまま親の所有物となって贈与関係が発生することになります。
子の受けた損失を建物の持分で代物弁済
しかし、贈与課税を発生させない方法があります。親が負担すべき工事代金を子が負担したにもかかわらず、リフォーム部分の所有権は親のものとなったのですから、子は自身の受けた損失に見合う償金を親に請求することができます。
一方、親にリフォーム工事代金を支払う資金がない場合は、子の償還請求に対し、工事代金の支払債務の返済を金銭の代わりに建物所有権の持分を子に代物弁済として移転させます。この場合、代物弁済を受けることについて、債権者である子の承諾が必要になります。
代物弁済には譲渡所得税が課税される
代物弁済は譲渡所得の対象となる資産の譲渡として扱われるので、譲渡所得税の課税対象となります。代物弁済により消滅する債務金額を収入金額とし、建物の取得価額を控除した残額が譲渡所得となります。
そこで代物弁済により消滅する債務金額と等価となる建物持分を子に移転させることによって、譲渡所得がゼロとなり、課税を回避することができます、例えば、リフォーム前の建物時価を300万円、リフォーム工事代金を1,200 万円、リフォーム後の建物持分の移転割合を 80%(1,200 万円÷(300万円+1,200万円))に設定すると、譲渡所得はゼロとなり、課税されません。
・収入金額=代物弁済する債務額1,200万円
・取得費=(300万円+1,200万円)×80% =1,200 万円
・譲渡所得金額=収入金額-取得費=ゼロ (短期譲渡・長期譲渡ごとに区分計算する)
リフォーム前に親から建物の贈与または譲渡を受けておくことも可能です。
なお、居住用財産を他の者と共有とするための譲渡、親子間の譲渡には、3,000万円控除や軽減税率の特例は適用されません。